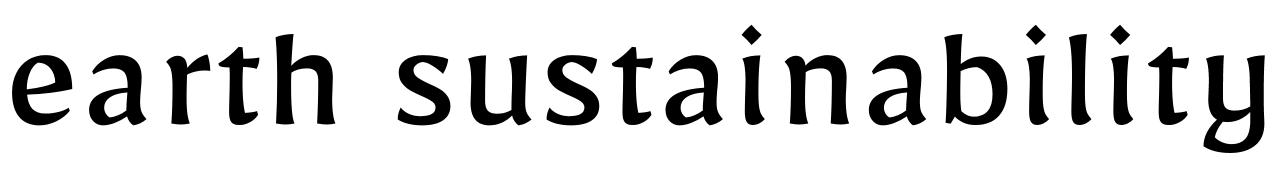Green Destinations(グリーン・デスティネーションズ)|持続可能な観光地の事例紹介

国内外には自然や風景など多くの人たちを惹きつける観光地がたくさんあります。そのなかでも地域住民と自然環境を配慮した取り組みをしている「持続可能な観光地トップ100」が毎年発表されているのをご存知でしょうか。
本記事では、Green Destinationsにまつわることと事例、そして関連ワードであるサステナブルツーリズムの概要を中心に解説していきます。
サステナブルツーリズムとは
サステナブルツーリズムとは、地域の自然環境・文化・経済を守りながら、地域資源を持続させ、かつ地域住民の暮らしをより豊かにする観光や旅行の取り組みのことを指します。
観光客の誘致をするために経済活動をしても、観光客によって地域の環境が乱れてしまったなどの現象があった場合、サステナブルツーリズムのコンセプトとマッチしない取り組みとなります。
エコツーリズム、グリーンツーリズムの意味とサステナブルツーリズムの違いについて
サステナブルツーリズムに紐づくワードとして、エコツーリズムとグリーンツーリズムの2つが挙げられます。それぞれのワードの意味は次のとおりです。
エコツーリズム
エコツーリズムとは、地域の環境や文化の保全を目的とした観光スタイルです。観光客に地域の素晴らしさに触れる、体験してもらうことで、環境保全と経済成長における良いサイクルができることを目指しています。
グリーンツーリズム
グリーンツーリズムとは、自然豊かな農村または漁村のある地域に滞在し、その土地の自然や文化、生活に触れながら、地域住民とのコミュニケーションを楽しむ余暇スタイルです。農業や漁業を体験しながら、地域資源の魅力も発見できるのが特筆すべき点となっています。
また、サステナブルツーリズム・エコツーリズム・グリーンツーリズムの違いは、サステナブルツーリズムがツーリズムの考え方全般を示しているのに対し、エコツーリズムとグリーンはそれぞれの観光の手段を表しています。

サステナブルツーリズムが注目される理由について
サステナブルツーリズムが注目される主な理由は、観光の大衆化です。
経済成長の影響によって安価でも旅行しやすい環境が整い、観光を楽しむ人が増えました。観光地に多くの人が訪れ地域活動に活気づいたのは良いものの、ゴミが増えた、マナーを守らないなどの地域の環境にダメージを与えるという「負」の要因が目立ち始めました。このようないきさつから、地域の生活環境の維持と、環境保全に絡んだサステナブルツーリズムが注目されるようになりました。
なお、日本では2018年に観光庁に「持続可能な観光推進本部」が設置され、観光客のニーズと観光地の地域住民の生活環境の調和に取り組んでいます。
2022年10月現在、海外からの水際対策が緩和され、観光目的で来日する外国人が再び増えています。サステナブルツーリズムがどのような展開になるか注目してみましょう。
Green Destinationsとは
Green Destinations(グリーン・デスティネーションズ、以下GD) は、オランダを拠点とする非営利団体であり、世界持続可能観光協議会(The Global Sustainable Tourism Council :略称GSTC)に紐づく国際認証団体です。
また、GDでは取り組むべき観光指標として 100項目を定めており、そのなかで最も重要とされている30 項目のうち、文化的資産の保護および保存など指定の15項目以上をクリアしていると「世界の持続的な観光地100選」にエントリーできます。
認証基準
GDが定めている認証基準は以下のとおりです。初年度と2年目以降の基準においては、項目数に違いがあります。
| 初年度基準 | 2年目以降 |
| ・ 訪問者のプレッシャーを管理する ・ 機密性の高いサイトでの訪問者の行動 ・自然保護と観光モニタリング ・動物福祉 ・ノイズ ・光害 ・廃水処理 ・廃棄物の分別とリサイクル ・再生可能エネルギー ・気候リスクへの対応 ・観光が文化に及ぼす影響の管理 ・人権 ・住民満足度 ・財産の搾取 ・サステナビリティ基準 | ・持続可能な目的地コーディネーター ・ 宛先資産のインベントリ ・目的地の管理ポリシーまたは戦略 ・観光による自然への影響への対応 ・ランドスケープ&シーナリー ・固形廃棄物の削減 ・旅行による輸送排出量の削減 ・エネルギー消費の削減 ・有形文化財 ・無形遺産 ・計画へのコミュニティの関与 ・地元起業家の支援 ・地元の商品やサービスの宣伝 ・健康と安全 ・企業のサステナビリティ推進 |
申請方法
申請の流れとしては、地域の担当者がレポートを作成することが必須であり、その内容に基づいて評価されます。認証された地域は、GDの公式ホームページに掲載され、「積極的に持続可能な観光に取り組む地域」として認められ、国内外に広く発信されています。
日本で選ばれた地域について
日本国内でもGDのトップ100に選ばれた観光地があります。ここでは近年の観光地を以下の表にしてまとめてみました。
| 2020年 | ニセコ町、釜石市、三浦半島、京都市、白川村、沖縄県 |
| 2021年 | 京都市、釜石市、ニセコ町、奄美大島、阿蘇市、長良川流域、七尾市および中能登町、那須塩原市、佐渡市、小豆島町、豊岡市、与論島 |
| 2022年 | 釜石市、阿蘇市、下呂温泉、箱根町、東松島市、南知多町、那須塩原市、小国町、大洲市、小豆島町 |
5年連続で選ばれた釜石市の事例
「世界の持続的な観光地100選」として選ばれた地域が、どのような理由といきさつで選出されたか知りたいという方もいることでしょう。こちらでは、2018年から5年間連続で選ばれた岩手県釜石市の事例について紹介します。
東日本大震災の被災地の一つである釜石市は、「漁船の活用による観光船の復活」をテーマに掲げ、震災で廃船という形になった遊覧船「はまゆり」を低コストで修復しました。観光客がいるときはクルーズ船として、漁業の繁忙機は漁船として活用することで、地域の漁師たちの所得向上などにつながりました。
また、釜石市は、岩手大学とも連携したプログラムも実施。乗船客に対し、採水した海水中のマイクロプラスチックのこと、海洋環境の変化や要因を学ぶ場を提供したことで、環境面への貢献の側面でも高く評価されています。

海外から人気が高い日本、サステナブルツーリズムに取り組む
サステナブルツーリズムは、日本でも耳にする機会が増えています。新型コロナウイルスの影響で2020年から2021年の国内外の観光が減りましたが、ここ最近、行動制限が緩和され、日本でも海外からの観光客が増えています。
また、日本政策投資銀行と日本交通公社(JTBF)が、「DBJ・JTBFアジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査(第3回 新型コロナ影響度 特別調査)」を実施したところ、「コロナ収束後に行きたい国ランキング」として、日本が1位を獲得しました。外国人にとって日本の印象は、食事が美味しく清潔感があるなどの理由で高く評価されているそうです。
日本は海外から人気のある国だからこそ、サステナブルツーリズムに注力し、観光客・地域の人・ツアー発案者の「三方よし」の関係性が築かれることが期待されています。
参照:
観光庁に「持続可能な観光推進本部」を設置しました | 2018年 | トピックス | 報道・会見