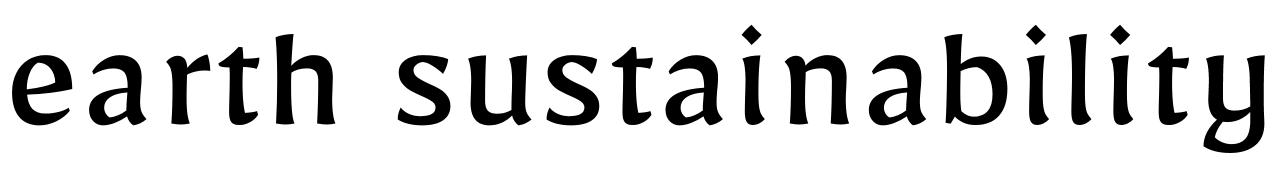昆虫食の未来を考える|コオロギを食べるプロジェクトから見える可能性

今回は、筆者が大学生を対象にした昆虫食を10,000人に食べて頂くためのプロジェクトに参加して、食の課題について感じたことを書いていきたいと思います。
そもそもなぜ、昆虫食が注目されているのか
現在私たちはスーパーへ行けば、食材に困ることも、値段が高すぎて手が出ない…ということもあまりないのではないでしょうか?
世界でも昆虫に関するスタートアップが増加したり、日本でも昆虫食のお菓子や食品、おしゃれなお店が増えていますが、なぜ注目されているのでしょうか?
理由の一つは「国連食糧農業機関(Food and Agriculture Organization)」が今後のタンパク質危機の救世主として昆虫食を推奨しているからです。
現在地球の人口は77億人ですが、今後2050年にかけて97億人まで人口が増加すると予測されています。それに伴ってそれだけの人口を賄うための食糧が必要になりますが、今の食糧生産の方法では気候変動のさらなる加速や森林伐採、水質汚染を引き起こしてしまうなど、持続可能な社会を目指すことはできません。
人間は生命を維持するために必要なものがいくつかありますが、その中でも今後特に不足してしまうのがタンパク質だと言われています。人は体内でタンパク質を生成も蓄積もできないため、常に外部から補給し続けないと生命を維持できません。私たちが1日に必要なタンパク質の量は体重の1,000分の1ですが、このままの食糧システムで人口が増え続けると、2050年にはタンパク質の需要と供給のバランスが崩れる「タンパク質クライシス」と言われる危機が起こると言われています。
コオロギに含まれるタンパク質

昆虫食と言っても蚕などさまざまなな種類がありますが、一番多いのはコオロギです。100グラム当たりのタンパク質量を比較すると「鶏は23.3グラム」「豚は22.1グラム」「牛は21.1グラム」。それに対してなんと「コオロギは60グラム」と圧倒的に多いのです。(※文部科学省 食品成分データベースより算出)
また、プログラムに協力してくださったエコロギー社のコオロギは雑食性という特性を活かし、カンボジアで廃棄されるお菓子などの残渣を食べるなどしてフードロスにも貢献しています。これは、牛や豚などの家畜に対して必要になる水や穀物の量、排出される温室効果ガスを比較するとほぼゼロに近い数値になります。
畜産業・農業から出る温室効果ガスの割合ですが、世界中で出されている全体の24%を占めるというデータもあるので、お肉ではなく昆虫食を食べることで温室効果ガスの削減にも貢献できるかもしれません。
コオロギせんべいとコオロギカレー
すでに挑戦された方もいらっしゃるかもしれませんが、エビのような風味がして美味しいということで、無印良品で販売されている「コオロギせんべい」を食べてみました。
初めはエビのような風味がして全く違和感なく頂けましたが、時間を開けて再度口にしてみると、本物のえびせんを想像してしまったからなのか、少し味が薄いように感じてしまいました。
また、チームのメンバーがグリラスという会社が出しているコオロギカレーを食べてみましたが、味の選択肢が「トマトカレー」「グリーンカレー」「イカスミカレー」となっており、メジャーな味ではありませんでした。
チームでは、普段食べ慣れている食事にコオロギなどの食材を加えると、食べる前に味を想像するため違和感を感じやすくなる可能性があると考えました。そのため、上記のような味の選択肢に限られているのではないかと思います。
昆虫食の課題
昆虫食と聞くと、いくら美味しく調理が行われていたとしても、ゲテモノというイメージが残ってしまいます。より多くの人に食べてもらうには、このイメージを変える必要があるなと感じます。
現在すでに多くの企業で商品化が進んでいますが、コオロギ粉末を使用して作られたお醤油やお味噌、お塩、チョコクランチ、バゲットやフィナシェなど、手に取りやすい商品かつパッケージをスタイリッシュにデザインできるかどうかも大切な要素なのではないかと考察しました。
また、まだまだ昆虫食やコオロギ食について知らない方も多くいらっしゃるので、実際に試食してみる機会を増やすことで、多くの人に存在を知っていただけるのではないでしょうか。
最後に
「衣・食・住」は私たちの生活に密接に関わっており、その中の「食」はやはりまず第一に「安全」そして「美味しさ」が必要だと感じました。
エコロギー社は昆虫食という珍しさではなく、味と栄養で勝負したいと老舗の醸造所マルマタ醤油と共同で「蟋蟀(こおろぎ)醤油」を開発しています。
口に含むと、濃厚濃厚な旨みやだし醤油のような甘味を感じることができるそうなので、みなさんもぜひお試しください!
参照:
【エコロギーCEO・葦苅晟矢1】コオロギ粉末で食糧危機とフードロス解消「代替タンパク質の切り札」 | Business Insider Japan
Gryllus Inc – 株式会社グリラス
無印良品