ミツバチが絶滅の危機に!保護に取り組む世界の企業・団体を紹介

ミツバチが絶滅すると、人類の未来はどうなるのでしょうか?
ミツバチは単なる小さな昆虫ではありません。彼らは食料供給の重要な部分を担い、果物や野菜の生産を支える受粉の役割を果たしています。
しかし、ミツバチの数が減少し続けると、その影響は私たちの生活に深刻な打撃を与え、人類の存続さえ危うくなるかもしれません。
本記事では、ミツバチが絶滅することで引き起こされる可能性のある危機と、私たちができる具体的な対策について詳しく解説します。
ミツバチが絶滅すると世界はどうなる?

ミツバチが絶滅すると、私たちの生活は大きく変わります。なぜなら、ミツバチは多くの果物や野菜の受粉を行い、これが私たちの食料供給を支えているからです。
具体的には、ミツバチがいなくなると、果物や野菜の生産が減り、食べ物が手に入りにくくなり、値段も高くなるかもしれません。
また、食物連鎖に影響を与え、ミツバチを食べる動物たちも生き残るのが難しくなります。ミツバチが絶滅すると、世界全体の生態系と私たちの生活が、大きな危機に直面する可能性が高いのです。
人類滅亡の可能性も
ミツバチの絶滅が進むと、私たち人類の未来そのものが危機に直面します。ミツバチは私たちの食べ物を育てるうえで、重要な役割を果たしているからです。
例えば、ミツバチがいなくなると、私たちが普段食べている野菜や果物、トマトやキュウリ、りんごなどが育たなくなります。スーパーの棚は空っぽになり、食卓に並ぶ食材が大幅に減ってしまうかもしれません。
この影響はパンやお肉にも及びます。ミツバチが受粉を行う飼料作物も減少し、牛や豚などの家畜が十分な飼料を得られなくなるため、肉や乳製品の供給も減少する可能性があるからです。
こうした食料不足が広がれば、社会全体が混乱し、私たちが安心して生活できる未来が失われる危険性があります。食べるものがなくなってしまうと、私たちは生きることができません。
ミツバチの絶滅は、私たち人類の存続さえも揺るがす大きなリスクなのです。
ミツバチは減少傾向にある
国連の報告書によると、過去数十年でミツバチを含む昆虫の数は急激に減少しており、その原因として農薬の使用や気候変動が挙げられています。
また、アメリカやヨーロッパの養蜂業者からは、毎年30%以上のミツバチ群を失っているというデータも報告されています。
これらのデータはミツバチが現在深刻な減少傾向にあることを示しており、私たちの未来のためにも、ミツバチの存在を守ることが重要です。
参照:
Humans must change behaviour to save bees, vital for food production – UN report | UN News
-UNEP emerging issues_ global honey bee colony disorder and other threats to insect pollinators-2010Global_Bee_Colony_Disorder_and_Threats_insect_pollinators.pdf
ミツバチ減少の原因は?
ミツバチが減少している原因には、いくつかの大きな問題があります。
まず、農薬の使用がミツバチに深刻な影響を与えています。特にネオニコチノイドという種類の農薬は、ミツバチの体にストレスをかけ、方向感覚を失わせることも。これにより、ミツバチは巣に戻ることができず、命を落としてしまうこともあります。
また、気候変動もミツバチにとっては厳しい環境を作り出す要因です。気温が上がったり、季節が不安定になることで、ミツバチが活動するタイミングがずれ、必要な花の蜜を集められなくなってしまいます。
さらに、都市が広がることで、ミツバチが餌を集める場所が減ってしまっています。以前は自然の中にあった草原や森が、今ではコンクリートの建物に変わり、ミツバチが生きていくための環境が失われている状況です。
私たちが少し意識を変えることで、ミツバチを守る手助けができるかもしれません。例えば、農薬の使用を控えたり、庭に花を植えたりすることで、ミツバチに優しい環境を作ることができます。みんなで協力して、ミツバチと共に生きる未来を守りましょう。
ミツバチが絶滅するのはいつ?
ミツバチが絶滅してしまうか、そしてその時期がいつになるかというのは、はっきりとはわかっていません。
ただ、現在の状況を見ると、ミツバチが減少し続けていることは確かです。このまま放っておけば、ミツバチがいなくなる未来が現実になるかもしれません。
心配しすぎる必要はありませんが、私たちがこのまま何もしないでいると、数十年後にはミツバチの数がさらに減ってしまう可能性があります。
気候変動が進むと、ミツバチが生きていくのに必要な環境がますます厳しくなります。
ミツバチ減少の対策は?
ミツバチを守るために、日常生活で実践できる方法を紹介します。
- オーガニックの野菜を選ぶ
- 植物を植える
- 食品ロスを減らす
それぞれの方法について、以下で詳しく説明します。
オーガニックの野菜を選ぶ

オーガニックの野菜とは、化学農薬や合成肥料を使わずに育てられた野菜のことです。
農薬や化学物質を使わないことで、野菜が自然のままの環境で育ち、土壌や水、そして空気に優しい方法で生産されます。また、ミツバチにとっても安全な環境が保たれるため、ミツバチが健康に蜜を集めることができます。
オーガニックの野菜を選ぶことは、私たちが日常生活で簡単に実践できるミツバチ保護の一つです。農薬はミツバチの神経に影響を与え、方向感覚を失わせることがありますが、オーガニック農法ではこうした影響を避けることができます。
さらに、オーガニック食品を選ぶことで、農家が安全な農法を続ける動機にもなり、ミツバチに優しい農業が広がることが期待されます。次回の買い物で、オーガニックのラベルを確認してみてください。それがミツバチを守る第一歩となります。

植物を植える

ミツバチは花の蜜や花粉を集めて生活していますが、都市化や農地拡大によって餌を集める場所が減少しています。そのため、自宅の庭やベランダにミツバチが好む花を植えることで、ミツバチの餌場を増やすことができます。
例えば、ラベンダー、ヒマワリ、ミント、タイムなどの植物はミツバチが好む花です。これらの植物は、手入れも比較的簡単で、季節を通して美しい花を楽しめます。また、ミツバチだけでなく、他の昆虫や鳥たちにも優しい環境を作り出すことが可能です。
植物を植えることで、ミツバチが元気に暮らせる環境を作ることができます。
食品ロスを減らす

ミツバチを守るためには、食品ロスを減らすことも重要な取り組みの一つです。なぜなら、食品ロスが減ることで、農業にかかる負担を軽減できるからです。
私たちが無駄にしてしまう食べ物が少なくなれば、その分だけ農地が不要になり、ミツバチの生息地を守ることにつながります。
例えば、食材を買う際には必要な量だけを購入し、冷蔵庫にある食材を無駄なく使い切る工夫をすることで、食品ロスを減らすことができます。
また、家庭でのコンポスト作りも、食材の再利用方法としておすすめです。これにより、ゴミを減らしながら土壌を豊かにし、自然に優しい生活を送ることができます。
日々のちょっとした工夫が、ミツバチを含む多くの生物にとって住みやすい環境を作り出す力になります。

ミツバチ保護をする企業・団体を応援する
ミツバチ保護に取り組んでいる企業や団体を応援することも、ミツバチ減少の対策につながります。
企業にとっても、ミツバチの減少は大きな課題とされていますが、それは「SDGsウェディングケーキ」に大きく関わっています。
SDGsウェディングケーキとは、SDGsの17の目標を「生物圏」「社会圏」「経済圏」の順に3つに分け、それらは積み重なってお互いに影響し合っているという考え方です。
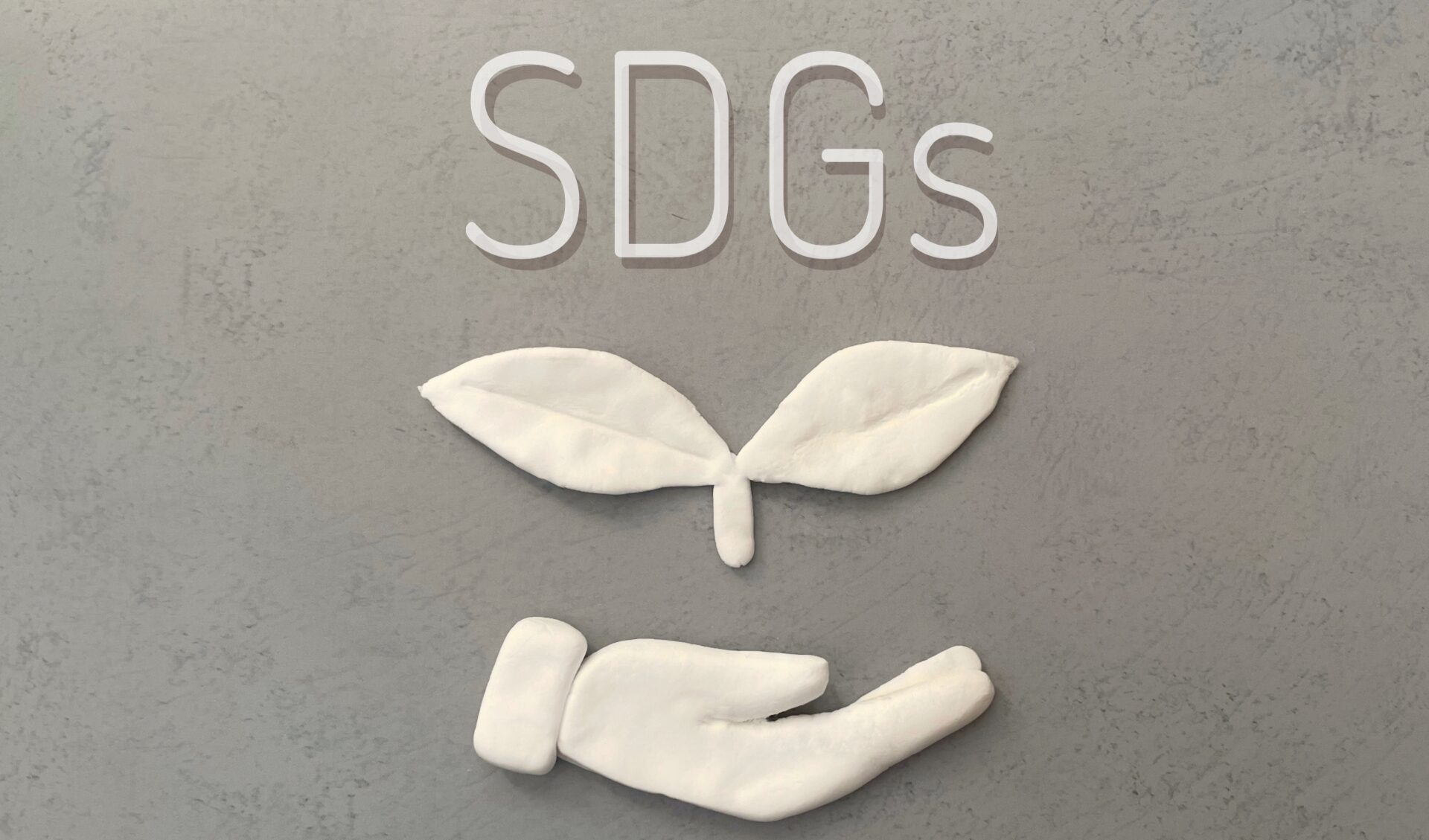
企業が健全な経済活動を行うためには、基礎を支えている「生物圏」の環境改善が欠かせません。ミツバチ保護に取り組んでいる企業と、その活動について詳しく見ていきましょう。
Unilever PLC.
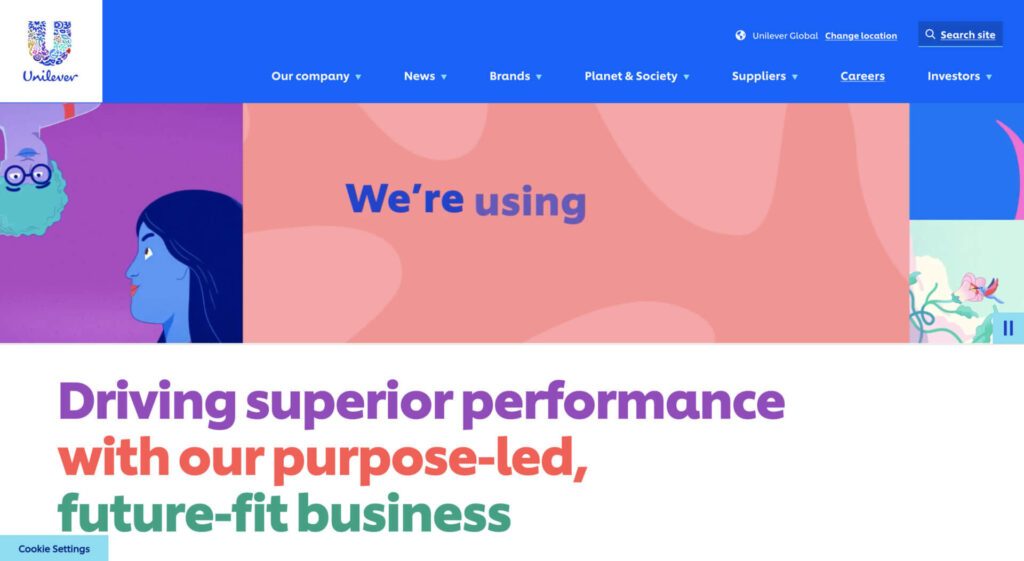
日本でユニリーバといえば、洗剤やヘアケア製品のイメージが強いかもしれませんが、実は世界的には食品メーカーとしても知られています。
ユニリーバが使用するアーモンドやマスタードシードなどは、ミツバチや他の受粉昆虫の助けを借りて生産されている作物です。
近年、農薬の影響でミツバチが大量に死んだり、行方不明になるケースが増えている状況です。ユニリーバは、ミツバチが生きやすい環境を守るため、生産者と協力してサプライチェーンの環境保護に取り組んでいます。
どれか一つでも要素が欠けると全体のバランスが崩れてしまうほど、生態系は非常に複雑です。そのため、ミツバチをはじめとする益虫を保護することで、土壌や水、空気、そして生物多様性全体を守ることができます。
具体的な例として、イギリスではマスタード生産者と協力し、ミツバチが好む生け垣や春の球根を植える活動を行っています。また、フランスでは野菜畑の周りに約2.85ヘクタールの花畑を作ることで、ミツバチの生息地を拡大中です。
さらに、ユニリーバのブランドであるクノールは、世界11カ国における20以上もの生態系保全プロジェクトに対し、34万ユーロ以上の資金を提供。ミツバチを含む多くの生物を守るための取り組みを進めています。
Les compagnons du miel
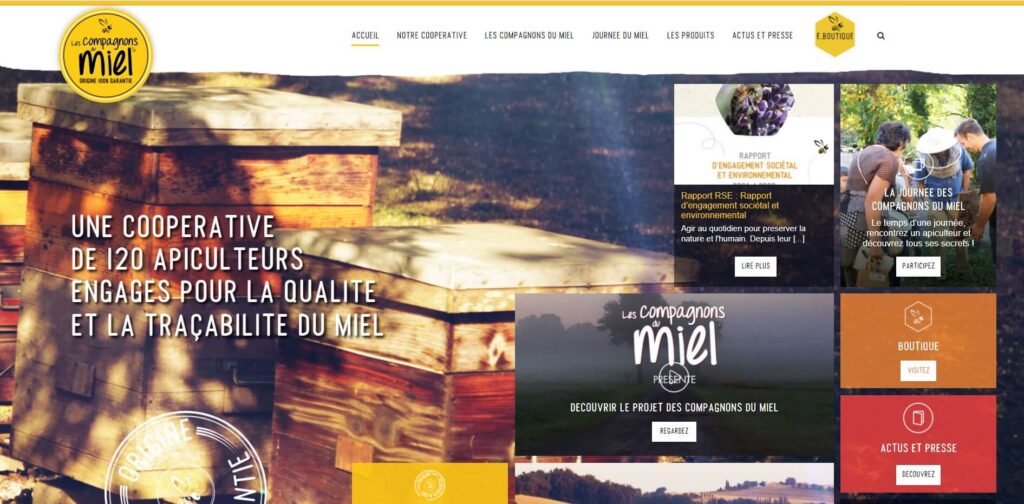
レ・コンパニョン・デュ・ミエルは、フランスとスペインにある120軒の養蜂家が協力して設立した協同組合です。
1958年以来、彼らは高品質の蜂蜜の生産に取り組み、製品の完全なトレーサビリティを確保してきました。これにより、消費者は蜂蜜がどのように生産されているかを透明性を持って確認でき、安心して商品を購入できます。
さらにレ・コンパニョン・デュ・ミエルは、養蜂家に公正な報酬を提供し、現地の雇用を守ることにも力を入れています。
環境に配慮した生産方法を実践しており、フランスのアグリエシークというフェアトレード認証を取得しています。この取り組みにより、蜂蜜がハチの巣から製品になるまでの過程で、すべてのステップがしっかりと管理されています。
レ・コンパニョン・デュ・ミエルの蜂蜜は、養蜂場によって風味や色が異なり、白っぽいものから黄金色、さらには深みのあるアンバー色までさまざまです。
フランス全土に広がる52,000以上のハチの巣は、何千もの植物種の受粉を助け、環境保護にも貢献しています。
BEE BETTER CERTIFIED
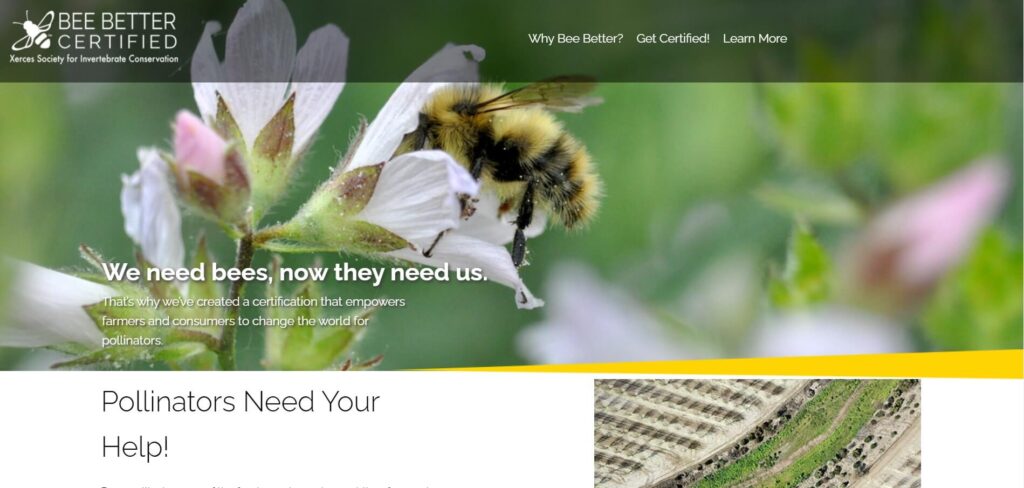
アメリカでは、ビー・ベター認定という取り組みが進んでいます。ミツバチやその他の受粉昆虫を保護するために、革新的な農法を採用する農家や食品会社を認定する制度です。
認定を受けた農場では、アーモンドやブルーベリー、野菜、リンゴ、ワイン用ブドウなど、多様な作物が栽培されており、これらの農場は約3,600種もの受粉昆虫にとって安全な生息地を提供しています。
農薬の使用を抑えることで、ミツバチや蝶をはじめとする有益な昆虫の保護にもつながります。
ビー・ベター認定を受けた製品を消費者が購入することで、受粉昆虫の保全を優先する農場が経済的な支援を受けることが可能です。これにより持続可能な農業がさらに広がり、ミツバチやその他の昆虫を保護できます。
SDGsやエシカル消費への関心が高まる中で、持続可能な農産物製品は消費者からの支持を集め続けています。
しかし、ミツバチへの影響を最小限に抑えて生産された製品については、まだ十分な認識がされているとは言えません。
ビー・ベター認定シールは、受粉昆虫の保護と生息地の確保をサプライチェーンに組み込むための象徴的なマークとして、今後さらに注目されるでしょう。
まとめ
ミツバチの減少がもたらす危機と、それに対する具体的な対策について紹介しました。
ミツバチの保護は、私たちの未来に直結する重要な課題です。ミツバチが絶滅すれば、食料供給に深刻な影響を与え、生態系全体のバランスが崩れます。それどころか、食糧不足に陥ってしまうため、人類にとっては大変危険な状態になります。
しかし、私たちが意識して生活するだけで、ミツバチ減少を食い止めることができるかもしれません。
オーガニックの野菜を選ぶ、ミツバチが好む植物を植える、食品ロスを減らすなど、一人ひとりが日常生活でできる小さな行動が、ミツバチを守る大きな力となります。
また、ユニリーバやレ・コンパニョン・デュ・ミエル、ビー・ベター認定のような企業が積極的に取り組んでいるように、企業レベルでもミツバチ保護に向けた動きが広がっています。
これからの未来を守るために、私たちもできることから始めてみましょう。
